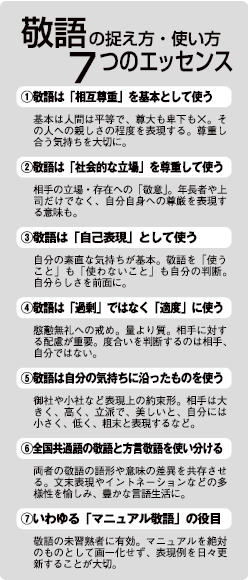|
知的おしゃれ=「敬語」の真髄と使い方 敬語は親愛や尊敬など他人への距離感の表現法。 |
|||
|
「著しい」を“ちょしい”と読む笑えない現実
ある新聞にこんな記事が載っていた。「乱高下」を「らんこうか」と読んだ女子アナ、「著しい」を「ちょしい」と読んだ新入社員、飲食接待でお店の女の子に照れた取引先のお客に「意外に厚顔無恥ですねえ」と言い放った男、「風説の流布」を読めない上に、意味も知らなかったマスコミ志望の学生など……のあきれた実態である。漢字や言葉遣いを知らない若者など、いまでは話題にもならないほどだ。その惨状に、社員教育のなかで漢字の読み書き練習や新聞の音読をして勉強させている企業がめずらしくないのだという。また一説では、一部の国立大学出身者をのぞくと、大卒の4人に1人は中学生レベル以下の漢字能力・語彙力しか身に付けてないとの指摘もある。 長年にわたる「ゆとり教育」のツケという見方が多いが、それはそれである。文部科学省ではこうした事態を重くみて、今年2月に公表した〈新学習指導要領案〉で「あらゆる学習の基盤となる言語の能力について、国語科だけでなく、各教科で育てることを重視する」と明記し、言語力強化を一大なテーマとして掲げ出した。 この背景には、OECDが定期的に実施している国際学習到達度(PISA)調査で日本の生徒たち(15歳児)の「読解力」が、前回調査で第8位であったものがさらに下降し15位にまで急落したことも大きく作用しているようだ。 見直しの契機が何であっても、また遅きに失した感があるにしても、“言語動物”とも言うべき人間が言語能力の退化に歯止めをかけ、強化にむけて手立てを講じることは、歓迎すべきことではある。問題は、こうした文科省の案に具体的な強化策が明示されていないことだ。 |
|||
| 言語能力は読解力、会話力等を含む総合スキル 童話作家でもあり出版文化産業振興財団理事長の肥田美代子氏のように、「言語力を習得する手段は読書である」とし、国語教育の指導順位を「話し・聞き・書き・読む」から「読む・書き・聞き・話す」への変更することを提言する(本年3月12日付読売新聞「論点」)人もいる。 しかし、この読書が言語能力に大きな影響を与えているのは確かだが、読書が万能の手法ではない。言語力は国語だけではなく外国語学習、方言、落語などの伝統話芸などでも養われることは文科省でも指摘している。肥田氏が読書を重要度第一位とするのは、いささか出版業界人としての我田引水論で、穏当さを欠いている。 むしろ、言語能力を広義のコミュニケーション能力と捉えた場合には「話し・聞き・書き・読む」の4つのスキルは、いずれも同等のものと捉えるべきであろう。そして人間が社会生活を営むにあたって重要なことは、この4スキルをさまざまな局面で、どのスキルについても過不足なく使えることだ。 いかに文章の読解力が優れていても、他人と普通の会話ができない人では困るし、逆にいかにしゃべりが上手くても、その場の雰囲気を考慮せずにしゃべりまくったり、気の利いた挨拶の手紙や礼状ひとつ書けないようでは、社会人として尊敬はされにくいのは明らかだ。 その点で、「話し・聞き・書き・読む」の4スキルの機能・要素のいずれにもさほど偏りなく関わっている言語ジャンルが「敬語」である。他人と会話をする場合にも、手紙を書く場合にも、ビジネス文書をしたためる場合にも、その意思をよりよく伝えるには、他人への親愛や尊敬の念、丁寧さ等を表現する「敬語」のスキルやセンスが不可欠なのだ。 当誌が、読解力不足、漢字能力の低下などを指摘されるコトバ崩壊の時代に、聞いただけでも堅苦しさを感じてしまう「敬語」を議論のテーマとした理由は、「敬語」の実践段階(=応用)における、コトバの本質的機能をすべて内包した“多様さ”や“奥行き”のゆえだ。 |
|||
| 成熟した敬語を使うことは、人間的成長の“果実” では、そもそも「敬語」とはどのような言葉であり、人間生活においていかなる役割を果たしているのか――。文科省・文化審議会委員の一人で、昨年2月「敬語の指針」の取りまとめにも参画された、お茶の水女子大学副学長・内田伸子氏(発達心理学)はこう解説する。 「敬語は、言語学上は下位カテゴリーに分類される一ジャンルでしかありません。そのなかでも社会的な対人関係の『距離』、つまり水平の距離感や上下の距離感を表わすマーカーであり、さらには相手への価値観(=評価)を表わす一種のシンボルでもあります。敬語は人間生活を営むうえでのコミュニケーションを円滑にする潤滑油の役割を果たす重要なスキルで、大人としてきちんと身に付けなければならない常識だといえます。 勘違いされては困るのは、人間は敬語を使うことで成長するわけではなく、人間が成長し、知的な向上が進み、教養が増してくると、対人関係やその場の状況に応じた言葉遣いが改まってくるということ。その結果が、より成熟した敬語や語彙表現が使えるようになるというのが順序です」 確かに、下表に示すとおり、3種類が5種類に分類項目が増えたとはいえ、敬語の仕組み自体は、基本の使用パターンも原理も難しいものではない。しかし、敬語もしくは敬意表現の厄介さは、この基本パターンを習得すれば事足れりとはならないことだ。むしろ、敬語の最も重要な点は、相互尊重の精神に基づき「相手や場面sに配慮して使い分ける言葉遣い」であること。そして、それらが相手の人格や立場を尊重し、敬語や敬語以外の様々な表現を駆使して「適切なものを自己表現として選択する」変幻自在(多角的)なものである点だろう(文化審議会答申『敬語の指針』より)。 |
|||
| 現代の敬語は、場面に応じた“アドリブ性”が大切 前出の内田氏は、自分のことを呼ぶ際に、相手や場面によって「オレ」「僕」「わたし」「わたくし」と使い分けること、大人に付き従う「お供」の連想から「子供」とせず「子ども」と表記するように変わった経緯、上の者が下の者を手伝ってあげるというニュアンスが色濃い「国際貢献」ではなく、同じ地平で一緒に力を合わせようという視点から「国際協力」という言い方が主流になっている……などの用例を取りあげ、社会生活における敬語を含む敬意表現は基本形はあるものの、定型として固定されているわけではなく、むしろ個々人の感性や場の空気によってじつに可変的であると指摘している。 実際、「敬語」は人間関係をうまく行なうコミュニケーションツールであるが、前述の「貢献」と「協力」との間のニュアンスの差異など、敬語や敬意表現の観点から区別して使う人はそれほど多くはいないはずである。 また、敬意表現は、言葉に限らないノンバーバルな要素も含めた話し手のその場面場面における振舞いや所作といったものも含むから、膨大な範囲に及ぶ。しかも、敬語は、最終的には老若男女を問わず、人間としての常識を踏まえた話し手本人の「自己表現」の側面が強いというわけだから、厳密にいえば、一つとして同じ心境や場面(ケース)に立った表現はないはずでもある。 その点、この敬語や敬意表現は、アドリブ表現(即興演奏)の連続といってよく、人間のコミュニケーション活動そのものといっても過言ではないほどの複雑さと拡がり(=多様さ)を持ってくることになる。 |
|||
| 敬語における「場を読む」ということと「KY」 かつては、いわゆる地縁・血縁の範囲内でのコミニュケーションが主流でありえた。ここでの「敬語」はしつけや行儀作法に近い固定的な構造を持っていたとみるのが普通だ。そのため、家庭内で身に付けるのがもっとも自然な手法とされてきたのであった。 しかしながら、現代社会では、人も金も情報も地域はもとより国家の枠を超えてグローバルに行き交い、見ず知らずの初めての人、不特定多数の人々との間でコミュニケーションが行われる。当然ながら、そこでは話し手と「相手」の立場や役割との関係、コミュニケーションの目的や内容、さらには方法なども場面場面で大きく変わり、多岐に渡ってくる。 そのため、敬語や敬意表現もますます多様で複雑になり、瞬時の判断が要求されている。そのベースとなるのが、立場やその場の雰囲気を即座に感じ取る能力、遭遇した「シーンの空気を読み取る」鋭敏な感性やセンスであることは明らかだ。言い換えれば、「人間力」ともいうべき、大切な総合センスが反映されるといえる。 閑話休題ながら、今日の人々の間で流行しているものに、「KY」という言葉がある。説明無用の人も多いはずだが、“空気が読めない”という意味の若者コトバで、「アイツはKYな奴だ」といった使い方をする。現代の社会生活をしていくうえで大切なのは瞬時に場の空気を読むこと。なのに、「その場の雰囲気を捉えられない鈍感なグズ」や「付合っても面白くないという人間」が多すぎるという感覚や思いが、この短縮語に込められている。それがいつの間にかおとなの間でも流行した理由というのが一般的な見方だ。 「敬語」は、良質の対人関係や社会生活を構築し、自らの存在を表現する手段でもある。それだけに、日常の場面場面において「敬語」を巧みに使い分けるられるか否かは、人間の出来・不出来、教養や知的レベルに直結していると指摘されるのも当然であろう。 |
|||
|
|||
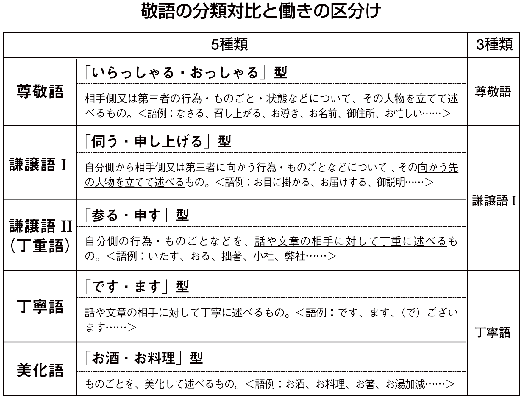 |